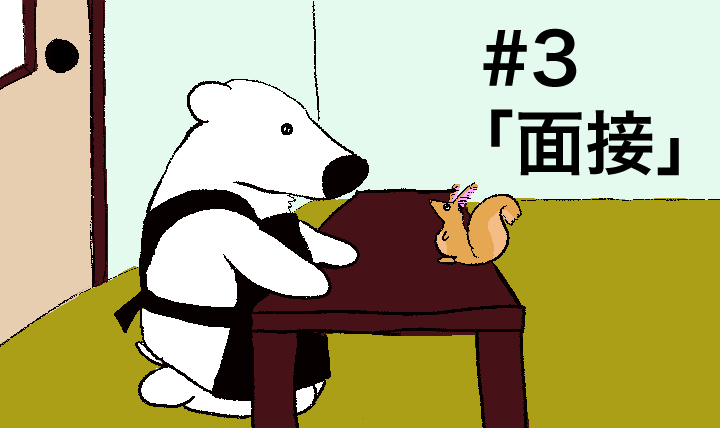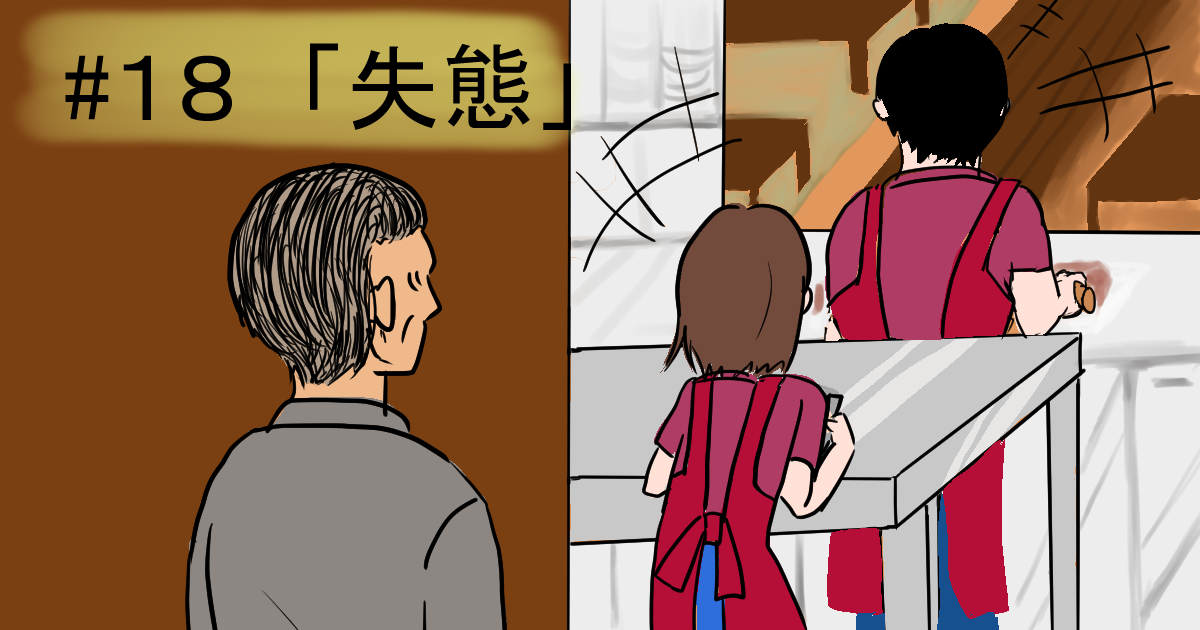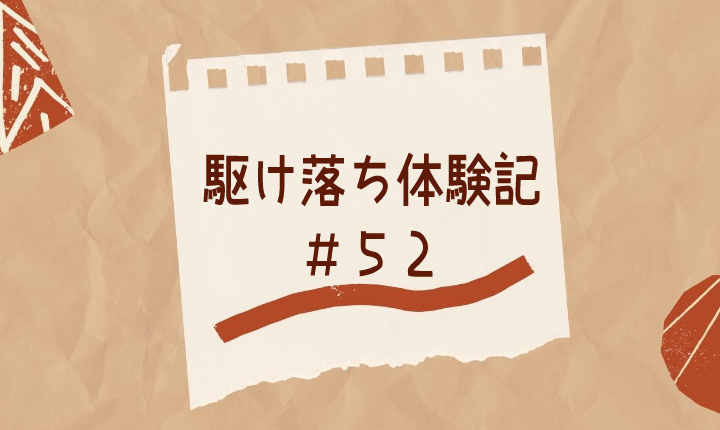#14「ド底辺」
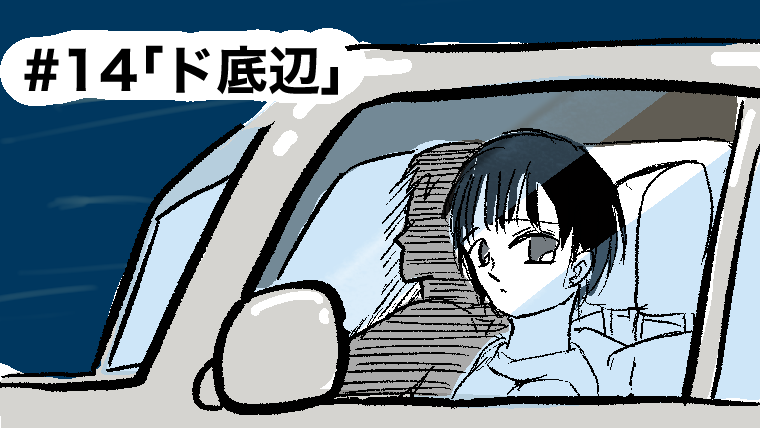
前回までの復習
自暴自棄になってか、単に流されてか、店長(未来の夫)の部下(妻子持ち)とカラダの関係を持った私。
同時期にクソ高い物(実際はそんな高くない)を騙されて買ったりだとか、とにかく私が人生で一番暗い頃の話である。
当時の記憶
思い出すだけで気分が滅入る。
けれども、この時代がないと私は夫に行きつかなかった。
この時の私の心情としては、竹内マリアの「マンハッタン・キス」の歌詞にとても近いと思っていた。
そのせいか、当時その曲をよく聴いていた。
歌詞の
「ここであなたが見せる優しさに偽りはないけど、どうしてこんなにさみしい」
「私より本当はもっと孤独な誰かがあなたの帰り待ってるわ」
によく自嘲していた。一体何に酔ってたんだか。
遊びと思っていたものの、あの頃はそう割り切ることもできていなかった。
「好き」と「愛し合う行為」をどうしても切り離せないくせに、どこかで「これは遊びなのだ」と勘違いさせていた。
誰かに対する優越感のようなものはあるものの、誰よりも孤独であることから必死に目を背けていたんだと思う。
抱かれてる間だけは考えないでいられたものの、それ以外の時間はずっと辛かった。
とはいえ、そのYさんとの関係もそう長くは続かない。
実際、関係を持ったのなんぞ、2、3週間の2、3回だったはずだ。
この頃、あまりに暗かったからか、母親に心配されたのを覚えている。
「アンタ、最近暗いけど、なんかあったんか?」
なぁんちゅこたない夕飯終わりに、キッチンから母にそう問われた。
常々思うが、母親の勘というものは異次元である。(現在進行形)
そしてこのYさんと関係したすぐあと、もう一人の部下Xさんと、車に乗って夜景を見に行ったことがあった。
それが、二人目。
Zさんとの夜
なんで一緒に行くことになったのか、その流れはもう忘れた。
私も相手も、そんなに深くは考えてなかったのだと思う。
ただなんとなくそうなったというだけ。
Zさんの車に乗って、どこかの山の上から街を見下ろす。
その光景すら全く覚えていない。
一緒に行ったのがもし夫だったのなら、きっと風景から感情から細かい会話に至るまで、詳しく覚えていただろうけど……。
夫とはとにかく感性が合うのか、しょうもない会話でもお互い覚えてたりして、いつまでもいつまでも会話が楽しかった。
でも行ったのはZさんなわけで、(おそらく)夜景見ながら会話してたはずなんだけど、気が付けばZさんの手が私の太ももの上にあり、
まぁ、その、なんというか…………
(ボソッ)そのままZさんといかがわしいことをした。
この辺りの! 詳しい内容は!! ゼヒ端折らせてくれっ!!!!
あと一応言っておくけど最後までは致していない!!!!(なんの免罪符にもならない)
直前? というか、途中で我に返った私が「この人ともそういうことするのはいかがなものか!?」と踏みとどまったからだ。
だが最後までシてないからといってなんの免罪符にもならない。(大事なことなので二回言いました)
とにかくこの時の私は、Yさんとは何度か致し、Zさんとは一回ヤる直前までキた。
と思って欲しい。
…………。
皆まで言うてくれるな。
このことに関して、私はいまだに後悔でいっぱいだ。
即終わる関係
そんな感じで、同時期にどっちとも爛れたコトになった。
それを止めようと思ったキッカケ、実はあんまり覚えてないけど、おそらく母親からの「アンタ最近ちょっとおかしいで」の一言やったような気がする。
「やっぱりおかしいか」
と、自分でも薄々今の自分はまずいんじゃないか、と思うほどには日常が異常やったと思うから。
大学もあったし、まぁ、YさんともZさんともお互いなんとなくで始まった交渉だったがゆえに、「こういうのはあれきりにしよう」と言えば、どちらもそれ以上触れてくることはなかった。
別れて、というか、男関係を清算して半月くらい経った頃かな。
いつも仕事を終え店長が売上の集計をしている間って、だいたいダラダラしながら雑談をするのが常だったりするのだけれど。
その日もいつものように、しょうもない雑談なんかをしていた。
会話の流れは忘れたけれど、たぶん女関係の話をしていたのだと思う。
その時の会話で、冗談でYさんが「じゃあ俺はおかやんに手を出そうっと」と言ったのだ。
冗談で言ったのだ。
そういう流れだったのだ。
だから、普通なら「なにいうてんねん!」とかそういうノリでサラッと終わるはずの会話なのだ。
だがその時の店長の驚いた顔といったら!
店長は明らかに「コイツマジで言ってんのか」という顔をした。
私も「コイツマジで言いやがった」と思った。
店長と目が合う。
その瞬間、私は確信した。
「(ああ。この人は知っていたのか……)」
いたたまれない私と店長を置いて、Yさんだけが何も気付かずヘラヘラと笑っていた。
こいつ最低だなと思った。
一時でも関係を持ったことを恥ずかしいと思うほど、心底から呆れた。
そして私は──
Yさんを見限るのと同時に、店長にすべて話すことを決意したのだ。