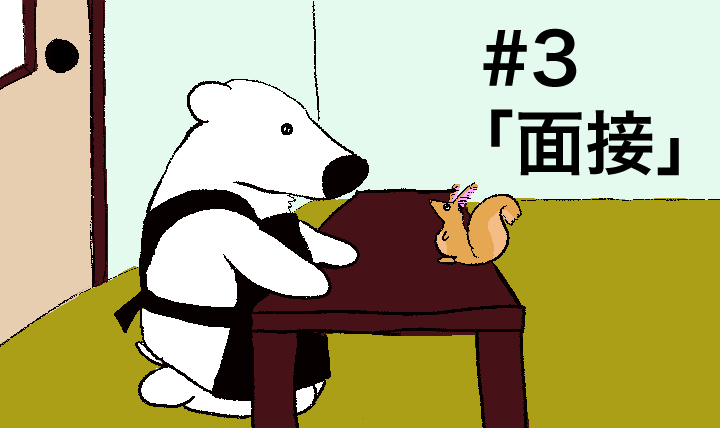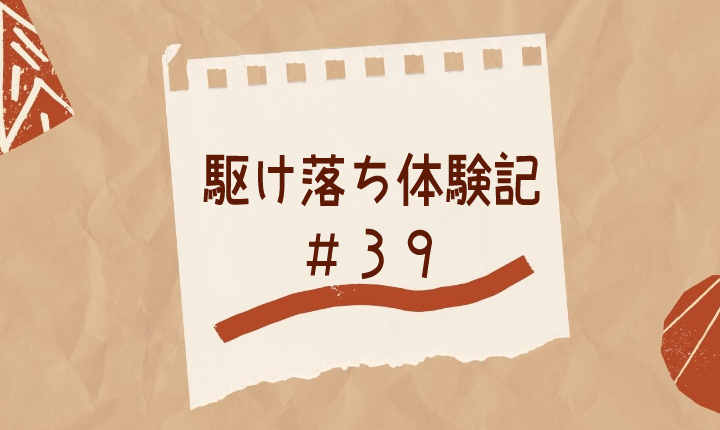#11「初デート」

初めてのデート
…………。
「初めてのデート」という見出しは、夫とのデートの時まで取っておきたかったなぁ……。
まぁ言っても仕方ない。
一応これも「そう」呼べるものだったのだから。
書いていて気付いたけどこの──先輩と初めて外で二人で会った時のこと、わりとしっかり覚えていたことに自分でも驚いた。
もう二十年も前のことなのに。
良い思い出じゃないからかな? 痛みや危険な目に遭った時の記憶は、自分の命に関わるから強く残りやすい、ってどこかで聞いたことがある。
その日。
時間よりほんの少し前、私は梅田駅にある太めの柱に寄りかかって、不安と期待で胸を膨らませながら待っていた。
人が多くて、騒々しくて、誰も彼もが忙しなく歩いていた。
Kくんのことは頭になかった。
ただ会えることが嬉しかった。……当時は。
そわそわとしながら行き交う波を目で追っていて、遠くに、ふと背の高い人が見えた。
サラッとした立ち姿で、でも筋肉質で、爽やかな雰囲気の男性だった。
受ける印象が素敵だった。なんとなく「あ。あの人カッコいいな〜。私ああいうのわりとタイプかもー」なんて思って眺めてたら、その人がこっちに駆けて来る。
え。と思ったのも束の間、近くまで来てやっと、それが待ち人の先輩だと分かった。
「ごめん。少し遅れた」
「い、いえ。大丈夫……ですよ」
本当に誰だか分かってなかった。
先輩は髪を切ったばかりで、パッと見の印象が違ってて、短髪好きな私にはなんとも言えない魅力があった。
見た目は本当に好みだったんだろうと今でも思う。
その瞬間のドキドキはなんともいえないトキメキがあって、そういう感覚って実はこれまであんまりなかったりする。
って、そんなこと言ったら夫がヤキモチ妬いちゃうな。でも、こればかりは理屈じゃないというか、意志とは無関係の「反応」だから私にはどうしようもない。一目惚れは遺伝子による一種の化学反応ときいたことがあるけど、それってきっとこんな感じなんだろう。
とはいえ、男を外見で選ぶとロクなことにならないが。
最低とはこういうことを言う
この時のことを思い出すと今でも苦々しい気分になるのは、それだけこの日が自分にとってしんどい出来事だからだろう。
自分の馬鹿さ加減や物知らずさを突きつけられて、反省を今でも繰り返す。
私が若かったように先輩もまた若かったのだろうけれど、それでも「本質がこういう人やったんやろな」と振り返って思う。
私にはやっぱり理解できないのだけれど、他人を傷付けて笑っていられる人って自分以上に大切にしたい人が存在しないのかな?
はてさて読者のみなさん是非に聞いていってくれ。この日何があったのか、その一部始終を。
駅で私が忘れものを返したあと、先輩は言った。
「せっかくやし、お昼一緒に食べへん?」
彼氏とは別れた。
つまり、今の自分に後ろめたいことは何もない!
目の前には新たに好きな人となった先輩!!
断る理由がどこにあろうか!?
「ハイ、行きます!!」
私は「待ってました」と食い気味に返事をした。
行ったのはモスバーガーだったかなぁ。食べ終わり、当時の私はまだコーヒーが飲めなかったので、アイスティーをちびちび飲んでいた。
部活の話。部員の話。関係のない話をしていたものの、次第に話題はフェリーでの夜のことへ。
そこへきて私は「これがタイミング!!」とばかりに、Kくんと別れたことを伝えた。
「あれ。おかやん別れたん?」
「はい。別れました」
「えー。なんでなんで?」
「や。その、色々あって、なんか無理になってしまって」
「もしかして俺が原因?」
「うーん……無関係ではないですけどでもこれは、私の……私たち二人の問題ですよ。先輩とのことがなくてもいづれ別れてたかもしれません。あの日あったことがどうのこうのじゃなくて」
「ふーんそっかー。……なんや。残念やな」
「? なにが残念なんですか?」
「えー……だって彼氏いる子とセッ◯スしたら、修羅場が体験できると思って俺楽しみにしてたのになー」
笑いながら、爽やかに、楽しそうに言った。
マジでこう言ったんだから、一周回ってもはや面白いとすら思う。
当時の私は目が点になったが。
「え? せ、先輩、修羅場になって欲しかったんですか……? 私の彼氏と??」
「うん。だって面白そうやし。俺の方が力あるっぽいからケンカになっても負けへん自信もあるし?」
「(なんかすごいこと言ってる……よう、な?)」
ちょっと何言ってるのか理解できなかった。
分からないからとりあえず謝った。
「は、はぁ……すみません……」
「いや。別に謝らんでもええけどさー。なんやー。そっかー。ふーん」
と本当に残念そうに言う。
「それでも」と望む心
そんな会話をしている店内では、大声で電話をしている女性の声が響き渡っていた。
その女性は別れ話をしているらしく、ずっと険悪に電話に向かって怒鳴っていた。
「なんやアレすごいなぁ」
「……そうっすね」
あの時のこの女性のように、素直に感情を表現していたらどれだけ良かっただろう。
私は好きであるが故に言いたいことも全部飲み込んで、ただただ先輩の望むように頷くことしか出来なかったのだから。
「で。おかやん。あの時のことやけど、俺の本気はあんなもんじゃないから。あの時はあんなんやったけどほんまはもっとスゴい」
「はぁ」(←私的にはそこはどうでもよかったし思ってもいなかった)
「証明するからもっかいせえへん?」
「………いいっすよ」
「マジで!?」
馬鹿でしょ? ええ、ええ。バカな女と一番呆れているのは他でもない私自身だ。
それでもこの時どれだけ嬉しかったか。
一緒にいられる喜びと求められる悦びがあって、その他なんてどうでもよくなっちゃったんだ。
「よっしゃ! あー……そうやなぁ『真っ昼間の今から』ってのもなんやし、先にデートでもしよか。初デートやな!どこがいい?」
「じゃあ映画が良いですっ!」
「ほんじゃ、それで!」
この時観た映画、今でもめっちゃ覚えてるわ。
忘れられへんもん。「マトリックス リローデッド」
映画を観ながら手を繋いだことも。ネオとトリニティのベッドシーンでやけに緊張したことも。
Kくんといたような未来が見えない状態……無味乾燥とした距離感なのに、カップルのように手を繋いでドキドキしたり。
本気じゃないのに好きな人が気まぐれに見せてくる優しさと甘さは、のちに経験する不倫とどこか似ていた。
私の内を駆け巡っていく多くの感情──楽しい。苦しい。嬉しい。切ない。痛い。つらい。好き。すき。
どれも忘れられない傷痕だ。
剣呑とした別れ話を続ける女性の怒鳴り声をBGMに、映画の時間まで雑談をしたこの会話も……忘れられない。
「このまま付き合う、とか先輩は考えないんですか?」
「えー、おかやんと? 俺とおかやんが付き合うってさ、なんか上手く行く気せんくない?」
「そうっすか?」
「セフレならいいけど、付き合うんはなー……難しない?」
「どうでしょう……?」
「俺とおかやんじゃ合わないって」
「そうですかね……」
「そうやで」
「……そう、っすね……」
それは付き合ってみないと分からないんじゃ、とすら言えなかった。
Kくんにはストレートに言えることが、先輩だと全然言えない。
歯切れの悪い質問ばかりを繰り返していたことを……覚えている。
だから結局最後まで「好きだ」と伝えられなかった。そんな言葉を望んでいないと察していた。
それでもみっともなく、回りくどく、先輩とお付き合いしたいと言ってみるのだけども、さっきみたいな言い回しで私の方から「出来ませんね」と言わせてくる。
そして言葉の端々に全力で「遊び」であることを匂わせる。
先輩の言うこの「無理」という言葉の真意を、なんとなーく理解できるのだけど、私にはどうにも納得できなくって。
でも実際、先輩と付き合ってる未来を想像出来ないのも確かにあって。
付き合ったところで上手くいかないであろうことも容易に予想できたのだ。
けれども引き返したくなかった。
どこかに愛情を見出したかった。
本当は体目的なのに気付いていたのに。
この時の私って──ああもう本気でバカ。
後悔先に立たず
そして映画を見て、夜になって、一緒に過ごして、終電で帰った。
泊まりはしなかった。
先輩にその気がなかったし。
事が済んだら急に素っ気なくなったのも良く覚えている。
満足して飽きたんだな、って本能的に悟った。
先輩が私に何を期待していたのかは分からないままだけど「思ってたのと違った」感がヒシヒシと感じられた。
あの、もやもやしながらホテルで過ごした数時間は……いま思い返してもどうにも空虚な時間だったな。
後悔とは、読んで字のごとく後から悔いるから「後悔」なのだ。
好きだから後悔しないと思ってたけど、経験してみたら好きだったから後悔しか残らなかった。
踏みにじられた心はズクズクといつまでも痛みうずく。これは今でもそう。
頭の良い人だったから(そういうとこも好きだった)、態度や言動から滲む私の気持ちに先輩は気付いていたと思う。
でも今だからこそ分かるし、断言できる。
相手の想いに付け込んで己の欲望の捌け口にすることは「男」のすることじゃない。
先輩からすればその行為は、単なる好奇心や興味本位だったかもしれない。
それもそれで残酷だ。
子どもが笑いながら蝶の羽根をむしり取るような、そういう無邪気な残酷さがある。
……お互いに利害は一致していたのだとしても、越えちゃいけない一線はあるのだと知っている。
そしてこの経験を経て、私はどんどんと歪んでいく。
男に絶望しながらも、のべつまくなしに「それ」を求めるようになっていった私。
……それって愛されたかったのに愛されなかった反動なのかな?
そこは未だによく分からないけれど、そんなふうにして崩れていった私の倫理観を正してくれたのは夫だった。
あの人に出会えたから、私はありったけの愛情であの人だけを愛していると言い切れる。
これを幸せと呼ばずしてなんと呼ぼう──。
夫以上に良い男なんて私の世界にはもう存在していない。
あの人だけが最高にして唯一無二の、私の自慢のパートナーだ。
ああ、やっと夫の話に戻れる。
だんだんと男に対してだらしなくなっていく私を、当時のあの人がどう見ていたのか知らないけれど。
このあとの私のやらかしが夫との付き合いへのキッカケとなる。
Kくんと別れ、肉体関係を持つことの敷居が下がり、口を開けば「彼氏欲しい」と言うようになった二十歳目前の私。
次に関係を持ったのは、当時の夫の部下だ。